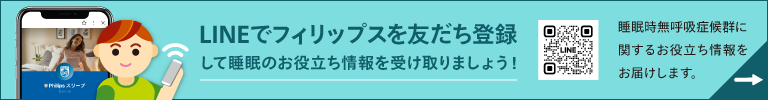オンライン診療について
治療方法について
オンライン診療とは
コロナ禍に認知度を深めた「オンライン診療」。厚生労働省が定める実施要件の緩和もあり、徐々にその普及率は上がっています。
オンライン診療とは、厚生労働省によると以下のように定義されていますが、自宅などにいながら予約や問診、診察、処方、決済等をインターネット上で行える診察のことです。
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。 引用:オンライン診療の適切な実施に関する指針|厚生労働省
スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、自宅等にいながら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。 引用:オンライン診療について|厚生労働省
病院に通院する必要がないというメリットがある反面、診療可能な疾患が限られていたり、最低一度は医師による対面診療が必要な場合があったりとデメリットもあります。ここでは、そのメリットとデメリットをもう少しまとめていきます。
オンライン診療のメリット
オンライン診療には、以下のようなメリットがあります。
1. 通院に関する負担が軽減される
インターネット環境さえあれば、自宅や外出先でも診療が受けられる点はオンライン診療の最大のメリットです。通院にかかる時間や交通費を削減することができるので、精神的、金銭的なコストを減らすことができます。 また、日中が忙しく病院に通いづらい方も比較的気軽に診察を受けることができる点もメリットと言えます。
2. 好きな場所で診察を受けることができる
既出のように自宅や外出先で診療を受けることができるので、例えば、近くに医療機関がなかったり、住んでいる場所が変わったりした場合でも信頼のおける医師に診てもらえる可能性があります。
3. 院内での待ち時間がなくなる
通常の対面診療の場合、受付、診察、会計それぞれに時として長い待ち時間が発生します。しかし、オンライン診療の場合、基本的に受付の必要はなく医師と患者の1対1でのビデオ通話のみとなり、会計もオンライン上での決済が主流となるため、待ち時間が発生することはほとんどありません。
4. 処方箋も発行される
オンライン診療では、診察後に処方箋を発行してもらうことができます。対応はクリニックによって異なり、紙の処方箋を自宅へ郵送してもらう場合や、希望する薬局へ送ってもらう場合もあります。
一方で、電子処方箋に対応している医療機関では、処方情報がオンライン上で薬局へ直接送信されるため、紙の受け渡しが不要です。これにより、薬局での待ち時間短縮や受け取りの手間が軽減され、診療から処方までをスムーズにオンラインで完結できます。
また、院内処方を行う医療機関の場合は、薬自体を自宅に配送してもらえるケースもあります。
5. 院内感染・二次感染を防げる
対面診療の場合、病院に行く必要があるため他の患者との接触を防ぐことは難しく、二次感染のリスクがあります。 オンライン診療であれば、他者との接触を防ぐことが可能となるうえ、自分自身が他者に感染を広げてしまうリスクも避けることができます。
オンライン診療のデメリット
メリットが大きなオンライン診療にも、もちろんデメリットはあります。
1. 診察できない疾患がある
すべての病気がオンラインで診察できるわけではありません。患者に直接触れることや検査等ができないため、そもそもオンライン診療が行えない病気もあります。 一般社団法人日本医学会連合が定めた「⽇本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提⾔」によると、緊急性や重症化の恐れがある症状が見られる場合や情報量や対応手段の問題がある場合等は、オンライン診察は適さないとされています。
2. 初診は対面診療を行う場合がある
疾患によっては、初診からオンライン診療が適用できないものもあります。その場合、少なくとも初診は対面診療が必要です。
3. 診断のために得られる情報が限られている
オンライン診療では、ビデオ通話による映像と音声のみで診察を行うことになり、当然ながら触診や聴診などの詳細な診察を行うことはできません。 そのため、場合によっては診断の精度が低くなる点があることは理解をしておくと良いでしょう。
4. 検査、処置や急変には対応できない
オンライン診療では、医師側が物理的に患者さんに触れることができないため、検査はもちろん負傷した場合などの処置を行うことができません。また、急変が認められた場合でも早急な処置を行うことができません。
5. 通信環境や電子機器の操作スキルにより診察が上手くいかないことがある
オンライン診療のビデオ通話は、スマホやタブレット、パソコンで実施されます。そのため、通信が良好ではない環境では診察自体が困難になってしまう場合があります。 また、オンライン診療専用アプリのダウンロードが必要となるケースもあるため、電子機器の操作に不慣れな方には利用が難しくなることがあります。しかし、そのような方には、電話診療が可能な病院、クリニックもあります。
睡眠時無呼吸症候群のCPAP治療はオンライン診療でも可能に
ここまで、オンライン診療のメリットとデメリットをご紹介しました。デメリットは当然ありますが、例えば、糖尿病などの慢性疾患では、オンライン診療と組み合わせることで継続的な治療が行いやすくなったり、育児・介護や仕事などで通院が困難だった方が受診しやすくなったりなど、メリットの方が大きいケースも多々あります。
睡眠時無呼吸症候群も継続的な治療が必要となる慢性疾患ですが、これまではオンライン診療対象外でした。しかし、令和6年度の診療報酬改定(2024年6月1日施行)により、CPAP治療(持続陽圧呼吸療法)については保険適応でのオンライン診療が可能となりました。 緊急性や重症化が少ない疾患と言われているため、オンライン診療のメリットを享受することが多く、例えば、働き盛りの方でも継続して睡眠時無呼吸症候群の治療を行いやすくなるかと思います。
治療可能な病院・クリニックでも、オンライン診療を実施しているところが増えて来ており、対応可能な医療施設は下記から検索いただけます。
なお、CPAP治療のオンライン診療は、最低一度は医師による対面診療が必要である旨が記載されていますので、その点を事前に確認しておくと良いでしょう。
- 睡眠時無呼吸症候群には、こんなリスクもあった
- 気をつけよう
睡眠時無呼吸症候群
- あなたのいびき放っておいて大丈夫?
- 知っておこう
いびきの基本